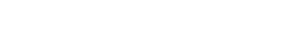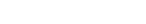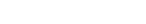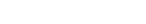初等教育科のお知らせ&トピックス
初等教育科の概要

本科は1953年に、まず保育専門学院としてスタートしました。その後、幼稚園教員養成所、初等教育科と次々に発展し、以来、大分県内はもとより九州地区において有数の実績と伝統を誇る幼児・児童教育における教員・保育士養成を行っております。
将来、小学校教育・幼児教育・保育分野の担い手となるべく豊かな人間性と知性・技能を身につけた人材の育成を目指し、現場の実際が反映されたカリキュラムを編成し、社会人への移行教育の視点からマナー指導や言葉遣い、文書作成指導等も実施しています。
また学生の自主活動である研究会活動を奨励し、学生の特性に応じて保育・教育の実践的な力が身につくように、担当教員が活動をサポートしています。
学びのポイント
保育士・幼稚園教諭・小学校教諭の3つの免許資格を取得可能
人格形成期の幼児・児童の教育に携わるエキスパートを養成
現場を重視したカリキュラムと実習活動
2年間の学びの流れ
1年次
保育の指導法、基礎技能を中心とする科目、保育の本質及び目的、理解等専門科目の講義、演習を行います。ピアノ・情報リテラシーは2年間通して学びます。3つの免許資格取得に応じた科目が開講されています。9月に小学校・幼稚園観察実習 2月に保育所実習を実施します。
2年次
1年次で学んだことを更に深め、総合的なもの、原理的なものも伝えていきます。専門職として子どもの心情を理解し、的確な援助ができる知性と技術を備えた教育者、保育者になるための講義や演習をします。保育所、施設、幼稚園、小学校の本格的な実習も行われ、学生の主体的、実践的な学びが多くなります。
私の大学生活
ピアノの練習環境と研究会の充実で進学を決めました
幼児教育の世界に興味を持ったのは中学時代の職場体験でした。高校を卒業したら進学して、幼児教育の資格を取ろうと思っていました。初等教育科のオープンキャンパスに参加した時に、ピアノの練習環境と充実した研究会の内容を聞いて進学を決めました。
入学した今では特に研究会活動に取り組んでいて「ハンドメイド研究会あっぷりけ」という研究会に所属しています。エプロンシアターという、自分で着たエプロンの上に小道具を置いてお話を進めていく遊びに力を入れています。ストーリーが楽しく分かりやすく伝わるように、みんなで工夫して作っています。
実習① 楽しさも大変さも両方味わいました
1年生の時に行った実習では子どもたちと触れ合うことが多く、たくさん一緒に遊んでとても楽しく学ぶことができました。食事や着替えの援助も行いました。
そんなある日15分ほど、自分が遊びを提供する時間をいただきました。1歳児クラスだったこともあり、手遊びをした後絵本の読み聞かせを行いました。子どもたちみんなの様子を見ながら、ちょうど良い速度で読み聞かせをするのが案外難しいんです。今のページをじっくり楽しみたい子、早く次のページに行きたい子、子ども一人一人の気持ちがあるので、なるべくみんなが楽しんで聞けるようにするのが大変でした。
実習② 学校の授業がこんなに生かせるなんて
実習に行ったとき、紙コップでロケットを作ることがありました。上手に教えることが出来たのですが、実はこれ授業で習った内容だったんです。造形表現の授業があって、紙コップでカエルのおもちゃを作ったり、絵の具で絵を描いたりしています。またおもちゃの作り方の図を、作り方のポイントを踏まえて描く、ということもやっていたので、日ごろから「このおもちゃを作るには、どう教えよう」ということを考えるクセがついていたんです。日々の授業が現場の保育に繋がって、授業を受けるモチベーションが上がりました。
幼児教育の大切さを学ぶ
高校の教員である父の影響で教員を目指すようになりました。幼稚園、小中高のどこで働きたいか考える中で、幼児教育が後の人格形成に与える影響が大きいことを知りました。いざ入学して勉強していくと、幼児教育の世界はとても奥が深かったです。自分達が子どもとして通っていた時のイメージとは違って、個々に合わせた指導や援助を行いながら子どもの主体性を大切にし、やりたいことを伸ばしていくことが重要なのだと学びました。
間違いなくいい環境
授業の中では実際に折り紙やお絵描きをして遊びを学ぶ場面があります。自分で実際にやってみてどう指導するのかを考えていくのですが、まずは子どもたちに取り組んでもらい、できたことを褒めるようにしていきます。その上で難しい折り紙やお絵描きにチャレンジするときは「こうしたらいいんじゃない?」ではなく、「一緒にやろう!やってみよう!」のように、子どもの可能性を広げる言葉かけをするように心がけています。
このような授業や言葉かけは現場を経験してきた先生がたくさんいらっしゃるからこそ可能なのだと思います。現場で子どもたちに教えた経験のある先生だと、実際の言葉かけや、その効果を細かく丁寧に教えてもらえます。そんな先生方がたくさんいらっしゃるので、環境には本当に恵まれています。
初めてのピアノ
入学して初めてピアノを触りました。幼稚園や保育園などで働く時にはやはり必要なので、まずはドレミファソを弾いたり、楽譜の読み方を覚えるところから始めました。
週に1回は個人レッスンがあり、毎週一生懸命練習して課題曲を弾けるように頑張っています。ちゃんと練習すれば弾けるようになるので、上達していくのが楽しいですね。
取得できる資格
- 小学校教諭二種免許状
- 幼稚園教諭二種免許状
- 保育士資格
- 社会福祉主事任用資格
- 認定絵本士
卒業後の進路
- 進路実績についてはこちら