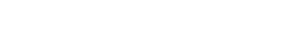コース概要
新しくなった充実の日本史・アーカイブズコース

日本史・アーカイブズコース」と「環境歴史学・文化遺産学コース」を統合しました。
- 読んで、歩いて学べ
- 記録と文書の扉をひらく探求へ
- 自然と人間のかかわりをさぐる日本史へ
- 現代と過去の暮らしをつなぐ民俗の世界へ
コースの特色
アーキビスト養成課程
日本では一般にあまり知られていない 公文書館(アーカイブズ)。博物館や 図書館とは違い、歴史的な史料(手書きの紙媒体、最近の電磁的記録、オーラルヒストリー(関係者から直接話を 聞き取り、記録として残すこと)など) を保管・管理・公開していく専門の施設です。本学では全国に先駆けてアーキビストの養成課程を設置し、現場主義の活動も多く取り入れながら学習していきます。主な現場実習としては、夏の中津 演習(合宿して本学や他大学の大学院生アシスタントに学びながら、昼は文 書の解読作業、夜は小講義、中間報告会など)、秋の大分県公文書館での実習(文書の整理やレファレンス業務体験など)が挙げられます。
自然と歴史そして民俗学の実習
別府大学では、20年以上にわたり国東半島の田染荘に入り、学生たちとともに景観保存に関わってきました。田染は国の文化的景観に選定され(2010年)、国東半島・宇佐地域は「世界農業遺産」に認定さています(2013年)。この実習では、日本の文化的景観の成立にも貢献した国東半 島や大分県内の荘園と故地で行われてきた荘園村落遺跡調査や環境歴史学的調査の手法をベースに自然と人間の関係史の調査法を学びます。古の時を超えて、今に生きる景観や芸能、行事、風習を現地に訪ね、地域の方との交流や体験を通して、昔の人々の想いや考えを読み解きます。それらの遺産や文化を保存し、後世へと伝えることのできる専門的な知識を持った人材を育成します。文化遺産の宝庫といえる大分県ならではの実地教育です。
日本史の舞台を訪ねる
2年に一度、国内研修(希望者制)が行われています。直近の研修先としては、長野県、石川県などが挙げられます。国内研修と海外研修を交互に実施しているので、希望すれば両方の研修に参加することも可能です。
※海外研修については"世界史コース"で紹介しています。
私の大学生活
震災をきっかけに歴史をかんがえるように
小さいころから、歴史のマンガを読んでいて興味を持つようになりました。高校生のころは日本史も世界史も得意で歴史を学びたいと思っていました。そんなときに熊本地震が起きました。熊本城が崩れて大きな話題になりました。熊本城ができる以前の熊本はどんな様子だったのだろうとふと疑問を抱き、別府大学に進学して深く学びたいと思いました。
考える歴史
大学で歴史を学ぶにつれ、歴史の出来事1つ1つに深い経緯があることに気づきました。例えば刀狩りについて、以前はいつの時代に誰が行った政策...という風に覚えていました。しかし掘り下げてみると、刀狩りの契機になった一揆の存在や、その一揆を起こすに至る経緯など様々な要因が重なって刀狩りという政策が出てきます。歴史の事実を「なぜ?」という視点で見るととても楽しいですね。
戦史
研究室では戦史研究室の室長をしていました。人間の戦いに関することを調べているのですが、第二次世界大戦、クリミア戦争、村同士の争いなど場所や時代問わずいつの時代も戦いは行われてきました。そのたび「人が犠牲になってお金が減る」と学んでいるのに、戦いは終わりません。まさに人間の本質という気がしますね。
本当の信長
私が研究したい時代は戦国時代で、主に織田信長と本能寺の変について現在勉強をしています。人気のある分野なので色んな研究者がいて、それぞれで唱える説が違って面白いですね。私はその周囲にいた人物などを調べることによって、本当の信長像が見えてくるのではないかと思って調べています。調べるにつれ、戦略家な一面や行動力のすごさが垣間見えてきました。
色んな分野を学べる
戦国時代の勉強の他にもたくさんの授業があります。学芸員の資格を取るための実習や、日本史を時代ごとに深堀した授業を受けてきました。特に南北朝時代の授業が面白かったのを覚えていますね。広くそして深く歴史について触れることができるのが良いところです。
少人数の授業
演習の授業では少人数で一つのテーマについて学んでいきます。担当の先生の指導ものと、明智光秀について調べていきました。ちょうど織田信長との関連があったのでとても面白かったです。時代ごとで考え方が違うので、野望を持って物事に取り組んだり、命の重さについての捉え方が違ったので面白かったですね。
講義ピックアップ
日本史特講2(日本中世史)
さまざまな中世史研究の流れをたどりながら、高校日本史の史料的・理論的な根拠を理解することを目的としています。
デジタルアーカイブズ
デジタルの知識や技術は勿論ですが、デジタル化が進行する社会で必須となる知的財産に関する知識も学びます。実際にデジタル撮影も行って実践力の向上も図ります。
専門演習 1・2(日本近世史)
受講者全員が前期・後期にそれぞれ1回ずつ、興味のあるテーマ(個々の発表テーマは多岐にわたります)についてレジュメを作成して発表をします。
アーカイブズ実習
江戸時代から明治・大正・昭和期の文書の整理方法を実践して身につけます。大分県公文書館での実習や、市町村の文書を実際に現地で調査することも行います。
履修モデル
1年
| 科目区分 | 科 目 | |
|---|---|---|
| 教養科目 | 基礎ゼミ | ◎導入演習(史学・文化財) ◎基礎演習(史学・文化財) |
| 学際科目 | ◎大学史と別府大学 ◎キャリア教育Ⅰ ◎インターンシップ基礎 ◎市民生活とアーカイブズ |
|
| 人間と文化の 探求 |
◎文学 ◎哲学 ◎日本文化史 ◎心理学Ⅰ ◎体育実技Ⅰ ◎体育実技Ⅱ |
|
| 現代社会の 多面的理解 |
◎法学(日本国憲法) ◎国際文化論1 ◎社会生活概論 | |
| 科学と情報 | ◎生物学 ◎情報リテラシーⅠ ◎情報リテラシーⅡ | |
| 国際理解の ための言語 |
◎英語1 ◎英語2 ◎TOEIC1 ◎TOEIC2 ◎中国語コミュニケーション1 ◎中国語コミュニケーション2 |
|
| 専門科目 | 共通専門科目 | ◎日本史概論1 ◎日本史概論2 ◎世界史概論1(西洋史) ◎世界史概論2(東洋史) ◎考古学概論 ◎環境歴史学概論 |
2年
| 科目区分 | 科 目 | |
|---|---|---|
| 教養科目 | 学際科目 | ◎インターンシップⅠ ◎ボランティア活動論 |
| 人間と文化の 探求 |
◎スポーツと健康 | |
| 現代社会の 多面的理解 |
◎社会学 ◎情報文化論 | |
| 国際理解の ための言語 |
◎英語3 ◎英語4 | |
| 外書講読 | ◎外書講読1 ◎外書講読2 | |
| 専門科目 | 共通専門科目 | ◎博物館概論 ◎デジタルアーカイブズ |
| 演習科目 | ◎発展演習1(史学・文化財学) ◎発展演習2(史学・文化財学) |
|
| 学科専門科目 |
◎アーカイブズ論Ⅰ ◎アーカイブズ論Ⅱ ◎アーカイブズ管理論Ⅰ ◎アーカイブズ管理論Ⅱ ◎日本史講義1(古代史料論) ◎日本史講義2(中世史料論) ◎日本史講義3(近世史料論) ◎日本史講義4(近現代史料論) ◎史学概論 ◎歴史地理 ◎民俗学講義 |
|
3年
| 科目区分 | 科 目 | |
|---|---|---|
| 教養科目 | 学際科目 | ◎キャリア教育Ⅱ |
| 外書講読 | ◎外書講読3 ◎外書講読4 | |
| 専門科目 | 共通専門科目 | ◎博物館学各論Ⅰ(博物館資料論) ◎博物館学各論Ⅱ(博物館情報論・経営論) |
| 演習科目 | ◎専門演習1(近現代史1) ◎専門演習2(近現代史1) |
|
| 学科専門科目 | ◎博物館実習 ◎アーカイブズ実習Ⅰ ◎アーカイブズ実習Ⅱ |
|
| コース専門 科目 |
◎日本史特講1(古代史) ◎日本史特講2(中世史) ◎日本史特講3(近世史) ◎日本史特講4(近現代史) ◎民俗学特講 |
|
4年
| 科目区分 | 科 目 | |
|---|---|---|
| 専門科目 | 共通専門科目 | ◎地方行政論 ◎地方自治論 |
| 演習科目 | ◎卒業演習1(近現代史1) ◎卒業演習2(近現代史2) | |
| 学科専門科目 | ◎国際交流論 ◎宗教史 ◎法制史 | |
| コース専門科目 | ◎卒業論文 | |