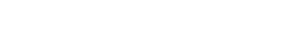コース概要
香りの専門家を育成

食品・飲料品やお酒、そして化粧品などの香粧品に含まれる様々な香りの成分について学び、生活を豊かにするための知識やスキルを身につけます。醸造発酵学に加えて、隣接の「大分香りの博物館」での実習をはじめとした香りについての実践的な教育を行うことで、食品産業から香粧品産業まで幅広い分野で活躍できる人材の育成を目指します。
コースの特色
食品・飲料品や化粧品などに含まれる香りについて学びます
食品・香粧品産業で活躍できるよう、食品生産、食品衛生、品質保持の要となる微生物に関する基礎知識を習得し、その上に食品や飲料品、化粧品などの香粧品に含まれる様々な香りの成分についての専門知識を身につけます。
今、ブームとなっている「香り」と日常生活のつながりを知る
日用品を中心に広がっている「香りブーム」ですが、食品の分野でもその魅力を増し、機能性を高めるためにフレーバー(香味)や香料などが重要な役割を果たしています。香料やアロマに含まれる香りの成分は、生活を豊かにする製品に欠かせませんが、一方で周囲への心配りも大切になります。本コースではフレーバーや香料そしてアロマに関する専門知識を身につけて、食品から香粧品に至るまで幅広く生活を豊かにするために必要な人材の育成を目指します。
私の大学生活
バイオを基礎から
高校では物理を選択していて、生物や化学はついていけるかが不安でしたが、問題なく勉強を進めてこられました。大学に入ってからは、まず1.2年生で研究をする基礎を学んでいきます。カビの種類や香りの分子構造、液体を成分ごとに分離していく実験、医学などいままで触れてこなかった分野が多く出てきます。これをもとにそれぞれのやりたい研究を進めていくようになります。
知識をフル活用
もともと食に興味があって、この学科を選びました。バイオや発酵を学ぶうちに、発酵食品がいかに人体に良い影響をもたらすかを知りました。そこで「動物にはどのように影響するのか」という疑問が浮かびました。バイオや発酵の技術がペットフードに使えて、ペットが健康に暮らせるようにするというのが私の今の目標となっています。これから本格的に研究ができるのでとても楽しみです。
失敗を重ねて学んでいく
大学の学園祭に向けて、ジャムを作って売ろうと作業を進めていたときのことです。買ってきたブルーベリーを使って、試作を何度も行い、いい具合の粘り気が出てきて美味しく出来上がりました。詰める容器もきれいに洗浄して、もうすぐ販売できると思った矢先、ブルーベリーの中に異物が入っていたことが分かりました。このまま出品することはできず、持ち帰りとなり、とても悔しい思いをしました。誰が悪い訳でもないので仕方無いのですが、この体験を通して食の安全性の大切さを学びました。
医療に興味があった高校時代
発酵食品学科の先生の中にがん細胞の研究をしている先生がいて、その先生の論文を読んだのが進学のきっかけになりました。内容は難しくてあまり分からなかったですが、医療系に興味があって進学を決めました。私自身がアレルギー体質なので、アレルギーに関する研究をして、困っている人の助けになりたいと思っています。
身近にいる微生物
私たちが普段口にしている食品の作り方を学ぶ授業がありました。砂糖や味噌、醤油などの原料と工程を深く掘り下げていくと、微生物の力なしでは成立しないことが分かりました。どのような微生物がどのように作用しているのか、1つずつ見ていくと「この商品は乳酸菌って書いてあるけど、あまり効果ないんじゃないか?」というように正しく食品を理解することができるようになりました。
香りの基礎から
香水には少なくとも100種類以上の香料が含まれています。その1つひとつに香りの持続時間があるので、香水は時間と共に香りが変わっていくということを学びました。香料をいくつか嗅いでみましたが、個人的には柑橘系やフローラル系がお気に入りでした。嗅覚は人それぞれ感度が違うので、感じ方の違いを調べるのはとても面白いですね。
講義ピックアップ
食品香粧学
香料成分の持つ様々な機能性について、香料成分の人体への作用機序を学ぶことにより、理解を深めます。香料成分のおいしさへの作用や、人体に及ぼす影響を理解します。
香料分析学
香料の成分分析法について学び、植物由来の天然物香料や調合香料を分析します。香りの成分の実体を最新の科学的分析法により捉え、香料についての理解を深めます。
香料学概論
昔から香料は人類の生活と深く結びついていました。過去からさかのぼって、香料が我々の生活にどのように関わってきたのか学習します。